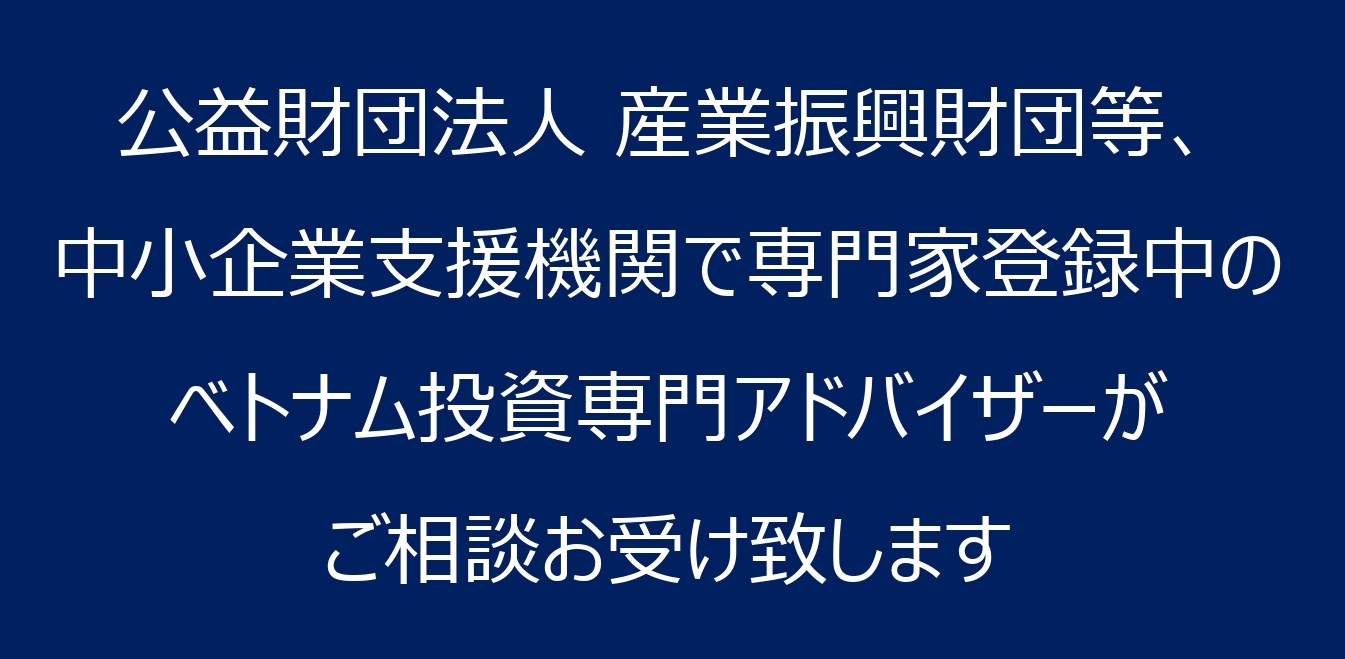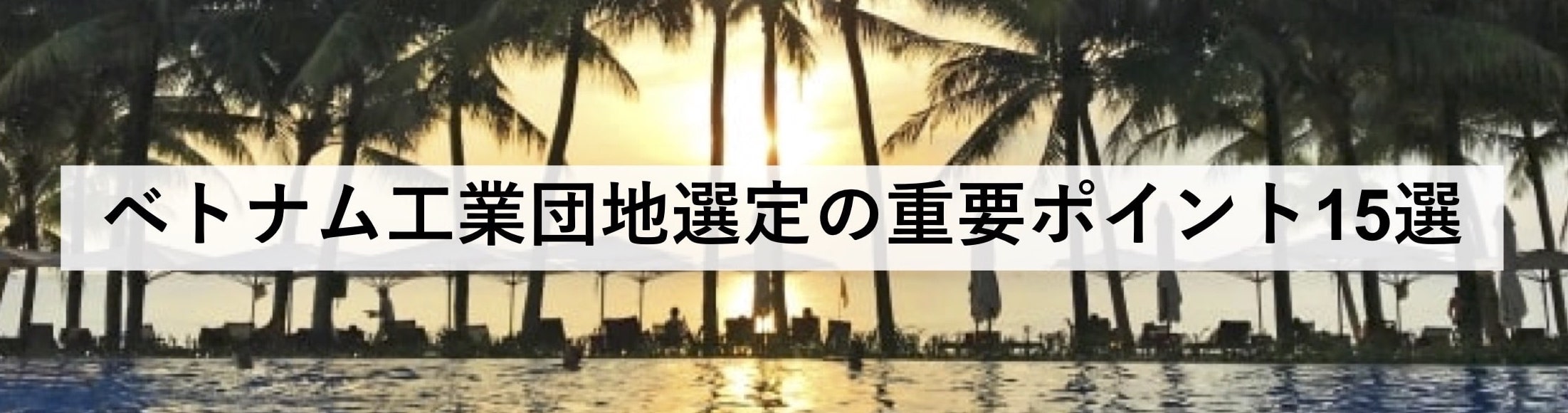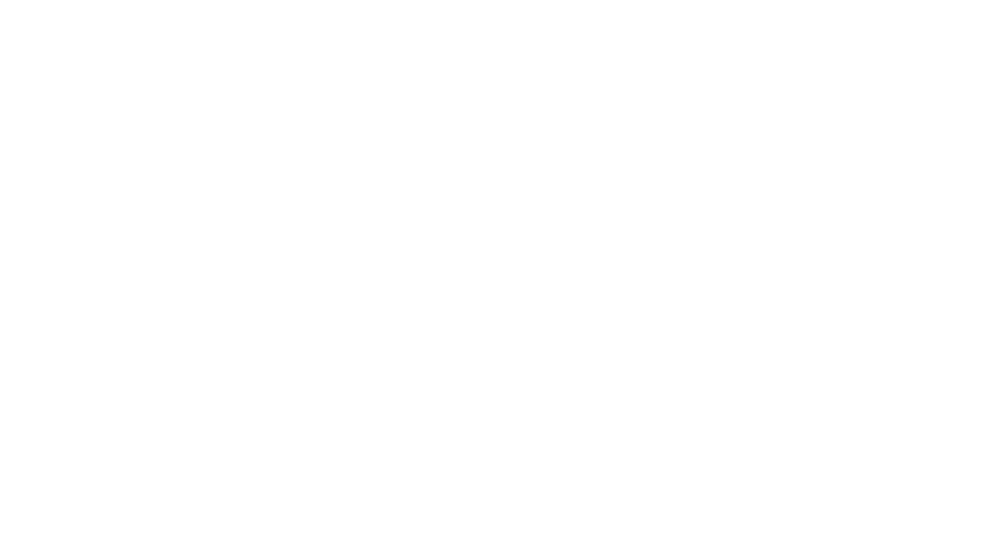ベトナム2024–2025制度改革 行政区画の再編・合併について
2025年7月から、ベトナムでビジネスを展開している企業の皆様、特に現地で直接投資(FDI投資)を行っている企業にとって、非常に重要な制度上の変化が始まりました。
これは、2024年から段階的に進められてきた「2024–2025制度改革」の一環として実施されたもので、従来63あった最上位の行政単位(省および直轄市)が、2025年6月12日までに34単位(28省と6直轄市)へと統合されました。
そして、今月7月1日より、新たな行政体制による正式な運用が開始。
今回の再編により、行政手続きの窓口や許認可の申請先、契約書や登記上の所在地表記などに変更が生じており、すでにベトナムで事業を行っている企業はもちろん、今後投資を検討されている企業にとっても、対応方針の見直しや制度への理解が急務となります。
本ページでは、「2024–2025制度改革」に基づく行政区画の再編・合併について、背景や概要、今後の留意点などを詳しくご説明いたします。
ベトナム行政区画の再編・合併2025に伴う「組織構造的な変化」
最上位行政単位の統合
◎ 従来:63単位(58省+5直轄市)
◎ 再編後:34単位(28省+6直轄市)
→ 約半数の省が統合され、行政単位が43%削減されました。
行政構造の簡素化
◎ 旧構造:3層制(省 → 県(district)→ 社・坊・特区(commune/ward/town))
◎ 新構造:2層制(省・直轄市 → 社・坊・特区)
→ 「県レベルの行政区画」が正式に廃止されました(2025年7月1日より施行)。
基礎行政区(社・坊)の統合
◎ 従来:約1万単位以上
◎ 再編後:約3,193単位に集約
→ 小規模な行政単位が大規模コミューンに再編成され、行政効率化が図られました。
新設・再編された主要な行政単位の例
◎ ダナン直轄市:ダナン市+クアンナム省
◎ ラムドン省:ラムドン+ダクノン+ビントゥアン
◎ ホーチミン市:ホーチミン市+バリア=ブンタウ省など(周辺省を統合)
本再編・合併の対象外だった(変化の無かった)エリア
以下の**10の省と1つの直轄市(ハノイ)**は、今回の再編において統合対象外となり、従来のまま維持されています:
▪️ 現状維持された「省」(10省)
◎ ラオカイ省(Lào Cai)
◎ ディエンビエン省(Điện Biên)
◎ ソンラ省(Sơn La)
◎ カオバン省(Cao Bằng)
◎ ランソン省(Lạng Sơn)
◎ クアンニン省(Quảng Ninh)
◎ タインホア省(Thanh Hóa)
◎ ゲアン省(Nghệ An)
◎ ハティン省(Hà Tĩnh)
◎ トゥアティエン=フエ省(Thừa Thiên Huế)
▪️ 現状維持された「直轄市」(1市) ハノイ市(Hà Nội)
※首都であり、政治的・制度的に特別な扱いのため再編対象外でした。
ベトナム行政区画の再編・合併2025の「推進理由」
此度のベトナム行政区画の再編・合併2025の推進理由は、以下の通りです。
◎ 行政効率化:
コスト削減:省単位および県単位の廃止により重複管理を整理し、行政コストの圧縮を図る
◎ 手続簡略化:
階層減により市民や企業の許認可が迅速化される見込み
◎ 経済競争力の強化:
統合によって地理的、経済的に規模が拡大し、投資環境整備や開発促進が図られる
◎ 政治的中央集権化:
共産党トップである総書記主導の「最も革命的な改革」と位置付けられ、政治的な統制力の強化が意図されている
ベトナム行政区画の再編・合併2025における「関連法令・制度変更」
党・政府の決議・方針
◎ 2024年4月の党中央委員会決議60により構想確定
◎ 2025年2月と4月に法改正・計画・実施準備決議(例:Decision 759、Plan No.47)
◎ 6月の国会で憲法改正を含む法改正と、新行政区画解决定議を通過
地方政府組織法等の改正
県(第2層)の廃止と社・坊等(第3層)の統合を法的に整備
ベトナム行政区画の再編・合併2025における「実施スケジュール」
◎ 6月12日:国会にて新自治体リストが承認 。
◎ 6月30日:各地で統合完了の宣言式、県レベル行政の終了宣言 。
◎ 7月1日:全土で統合マップと2層ガバナンス構造が正式運用開始 。
◎ 後続:8月末までに省レベルの調整、年内完全運用予定 。
ベトナム行政区画の再編・合併2025における「現状」*2025年7月以降
◎ 省・直轄市:
28省+6直轄市が運用中。特例として、ホーチミン市はビンズオン・バリア・ブンタウ省、ダナン市はクアンナム省など、いくつかの省との合併例あり。
◎ 県レベルの廃止:
憲法改正により、2025年7月1日から正式に県レベルの行政区が消滅
◎ 基礎行政区再編:
社・坊・特区の統合により、従来の約1万単位を3,193単位に縮減

ベトナム行政区画の再編・合併2025における「課題」
◎ 行政手続きの過渡期における実務上の調整:
新たな行政単位の発足に伴い、許認可関連の書類における住所表記の変更、ならびに各省・直轄市ごとの運用基準の違いなど、一定の調整が必要となる場面が生じています。現地では、各地方当局が順次対応を進めており、手続きの円滑化に向けた移行期間として受け止められています。
◎ 人員再配置を中心とした組織体制の見直し:
県レベルの組織統合を受け、これまで該当業務を担っていた省庁や関係機関の職員については、退職勧奨や再配置が段階的に進められています。一部では人員過多となる部門も見られる中、各地方での再吸収策や新たな配置先の整備が今後の焦点となっており、行政機能の維持と人材活用の両立が求められています。
◎ 地域的な特色の継承に関する配慮:
複数の省や郡が統合される中、それぞれの地域がこれまで維持してきた文化や伝統、呼称への愛着に対して、一部住民からは惜しむ声も聞かれます。行政の効率化が進む一方で、地域ごとのアイデンティティや風土をどのように尊重し残していくかが、今後の本制度の重要な視点となっています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上、ベトナム行政区画の再編・合併2025について、ご説明致しました。
2025年7月のベトナム行政区画再編の施行以降、全国各地でさまざまな問題やトラブルが報告されており、ベトナムで投資やビジネスを行う外資系企業も様々な影響を受けています。
行政区の統合に伴い所在地や登録住所が変更となったケースが多く、これに関連する法人ライセンス変更(登記変更)や営業許可の更新手続きが複雑化し、時間とコストの増大を招いています。
県レベルの廃止により従来の県役所が閉鎖または機能縮小された地域では、新たに統合された省または直轄市の窓口が十分に整備されておらず(新しい管轄当局の業務体制がまだ整っていない地域も多く)、手続きの遅延や窓口の混乱が発生しており、外資系企業は迅速な対応が難しい状況です。
さらに、投資関連の法規制や許認可基準の地域差が拡大し、複数地域にまたがる事業展開においては対応が煩雑化しているほか、言語や制度の理解不足も重なり、現地パートナーとの連携や情報収集に支障をきたすケースもあります。加えて、行政担当者の再配置や人員削減による専門知識の不足が、一部の審査や許認可プロセスの質低下や不透明化を招いていており、現地に投資した外資企業からは「迅速に対応してもらえない」、「行政に問い合わせてもまだ対応が決まっていないと回答された」と言った声も上がっています。
こうした状況は外資系企業の投資計画や事業拡大の意思決定に影響を及ぼし、不確実性が高まっているため、リスク管理や法務面での慎重な対応が求められます。
総じて、行政再編に伴う制度移行の混乱が、外資系企業にとっては投資環境や投資の決定における一時的な不安定要因となる可能性もあります。
ベトナム2024–2025制度改革 行政区画の再編・合併への「期待」と「利点」
確かに、今回の行政区画再編に伴い、現場レベルではさまざまな課題や混乱が報告されていますが、とはいえ、一方で、今回の制度改革には中長期的に見た際の明確なメリットや、将来的な期待も多く存在します。
まず最大の利点は、行政運営の効率化と簡素化が図られることです。
従来の三層制(省→県→社・坊)という縦割りの構造を廃し、二層制に統合することで、意思決定のスピードが向上し、重複した行政業務の削減によるコストの抑制が可能になります。
これにより、行政手続きの迅速化と透明性の向上が期待され、特に外資系企業や大規模プロジェクトにおける申請・認可のリードタイムが短縮される効果も見込まれています。
また、行政単位の再編によって広域的な開発戦略の立案がしやすくなり、インフラ整備や都市計画、産業誘致などをより効率的・一体的に推進できる体制が整います。
従来は省単位でばらばらに進められていた政策が、統合された新行政区内でより統合的かつ戦略的に行われることで、経済のスケールメリットや地域間の格差是正につながる可能性があります。さらに、行政機関のスリム化によって、公務員の質の向上やIT化・デジタル化の導入促進も期待されており、長期的には行政サービスの全体的な質的向上にもつながります。政治的には中央政府の統制力が強まり、国家戦略の遂行や危機対応力の強化にも資する側面があります。
また、これまで地方ごとに異なっていた制度運用のばらつきを解消する方向での整備も進められており、法制度の標準化・一元化が進むことで、投資家にとっての予見可能性や安心感も高まっていくと考えられます。
以上のように、短期的には混乱もあるものの、中長期的にはより洗練された行政体制の構築、統一的で安定したビジネス環境の形成に向けた前向きな改革であるという見方もでき、投資環境の更なる改善が期待されています。